第37回北海道公立学校事務長研究協議会
去る9月12日、13日の2日間、ホテルライフォート札幌を会場に会員223名の参加のもと、第37回北海道公立学校事務長研究協議会が開催されました。
主催者挨拶
【北海道公立学校事務長会会長 坂井 秀昭】
開会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。
本日は、全道各地から多くの会員の参加をいただき、第37回北海道公立学校事務長研究協議会を開催することができましたことに、心よりお礼申し上げます。
また、日頃より本会の活動に、多大なるご支援をいただいております、北海道教育委員会様、北海道高等学校長協会様、北海道特別支援学校長会様、公益財団法人日本教育会北海道支部様、そして全国公立学校事務長会様には、ご多忙な中、ご臨席を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、本研究協議会も37回を迎え、これまで全道各支部の会員の活発な研究活動に支えられ、多くの成果を上げてきました。今年度は、根室・釧路・オホーツク・十勝と、4つの支部による研究発表が予定されておりますが、私たちが日常業務の中で抱える問題や課題を解決するための一助となり、本研究協議会が有意義なものとなるよう期待しているところです。
本来であれば、この、第37回の研究協議会は、昨年9月に開催される予定でしたが、「台風21号」と「胆振東部地震」という二つの災害に相次いで見舞われ、大会直前で急遽中止の決定をせざるを得ませんでした。
しかし、昨年発表することが叶わなかった貴重なこの4つの研究発表は、一年の時を経まして、今大会で皆様の前に披露される運びとなり、非常に嬉しく思っております。
それでは、私から2点申し上げます。
1点目は「全国大会」についてです。去る8月1日・2日の2日間にわたり、東京都において、第43回全国公立学校事務長会研究協議会が開催されました。
少しご紹介しますと、初日の高校の分科会では、兵庫県から、5年間にわたる「研修の体系」というものを策定し、その計画に沿って「次世代職員育成研修」、「新しい時代のマネジメント研修」など、活発に研修活動を進めてきた実績についての発表がありました。
また、特別支援学校の分科会では、「防災対策」をテーマに、全国アンケート調査結果を基にした、災害への対策、全国の現状などについての情報交換や協議を行いました。
そのほか、二日目には、福岡県から、学校の活性化を図るべく、民間企業との連携や、ドローンを利用した特色ある授業の導入という取組についての研究発表が行われました。
どれも他県の事務長さんが一生懸命取り組んでいる状況を知ることができ、非常に為になるものでしたし、人材育成や少子化の課題を抱える北海道でも参考とすべきところがあるのではないか、そのように思いました。
そして、来年度の全国大会は、青森県青森市で開催されます。この青森大会では、北海道が研究発表を行います。テーマは、これまで本部調査研究部が取り組んできました「異動時の引き継ぎ事項」を基に、現在全国の各事務長会へ依頼しているアンケート調査の結果を絡めまして、内容を更に充実させたものとなる予定です。
青森市は、全国大会の開催地としては、北海道から一番近い場所でもあります。この機会に是非一人でも多くの方に参加していただき、北海道からの、そして全国からの研究発表を聴いていただければ幸いです。
更にその2年後の、令和4年度には、北海道で全国大会が開催されます。その節は、どうか皆さんのお力添えをいただきますよう、お願いいたします。
次に2点目ですが、本道における課題であります「事務改善」について申し上げます。平成29年1月に道教委へ提出した提言に基づき、昨年度、一部の管内で事務改善に係る検証会議が実施されましたが、今後は更に全道的に広く意見交換の場が設定されることとなる見込みですので、全道の事務長の皆さん、事務職員の皆さんの多くの声が反映されることを期待します。
また、ここ数年、働き方改革についての取組が進められています。道教委により「北海道アクションプラン」が策定され、見直しなども図られながら、適正な勤務時間と健康管理を意識した、より実効性のあるものへと整備されてきています。
校種や学校規模により業務量などに差があることは否めませんが、それぞれの学校における働き方改革を進めていくためには、業務の効率化・省力化がこれまで以上に求められていることは確かです。
本会としましても、事務改善が学校事務室にとってより良いものとなるよう検証を進めていくとともに、結果としてそれが働き方改革の推進に繋がっていくものと信じ、今後も業務の効率化・省力化を進めるとともに、「学校運営の機能強化」に向けた研究を継続してまいります。
このほか、学校現場においては、人材育成の取組など、様々な課題が山積しております。日々の課題に対峙しながら事務長として学校経営への参画を推進していくために、私たち自身の資質の向上が求められています。
本会は、その責務を果たすべく、皆さんとともに、これらの課題についての調査・研究活動を推進し、教育の発展に寄与してまいりたいと思っています。
本日は、この後、公益社団法人日本テニス事業協会スクール部会長 蒲生 清 様による「スポーツ産業の現状とテニスに学ぶ教育のヒント」と題する講演をいただき、2日間にわたる研究協議を開始することになります。
最後になりますが、この研究協議会の開催に当たりまして、昨年、今年と、2カ年にわたり、企画・運営に大変ご苦労いただきました、後志支部の皆様に心から感謝申し上げますとともに、本大会が大成功となりますよう、ここにお集まりの皆様に、改めてご協力をお願い申し上げ、開会の挨拶とさせていただきます。
ご来賓挨拶
 北海道教育庁総務政策局長 池野 敦 様
北海道教育庁総務政策局長 池野 敦 様
事務長の担い手不足の現状に対し、複数回の選考を実施するも来年度昇任者の確保に至っておらず、部下職員への一層の働きかけを行って欲しいこと、増加している30歳以下の若手職員が早期に学校事務の中心を担う状況を想定し、学校でもOJT等を通じた育成に努めてほしいとの要請がありました。
また、財務会計の適正執行について、毎年度事故が発生し保護者や地域の信頼が損なわれることから、引き続きコンプライアンスの確立に配意願いたいとのお話がありました。
北海道高等学校長協会会長 宮下 聡 様
職員の働き方にも見直しが求められるなど、大きな教育改革の波に晒される中で「不易」と「流行」を見極めつつ、未来を託すにふさわしい子どもたちの教育を進めていく必要があるとのお話をいただきました。
また、今年度の文教施策要望は子どもたちの教育に関わる事項に焦点化した内容としており、今後も要望の実現に向けて協議を深め対応を働きかけていきたいとのことでした。
北海道特別支援学校長協会会長 木村 浩紀 様
年々変化する学校事務を取り巻く状況の中で、事務長や事務主任のなり手不足、働き方改革として人事評価制度を活用した意識改革、学校閉庁日、出退勤管理など、学校事務の効率化・省力化を図る一方で、職員一人一人の仕事に対する意識を高めることが求められている現状に触れ、チーム学校として協働する組織作りが重要とのお話しをいただきました。
また、特別支援学校のセンター機能による地域支援や地域との連携を通じ、特別支援教育の充実発展を図っていくため協力をいただきたいとの要請がありました。
ご来賓紹介
 日本教育会北海道支部事務局長 蔵本 康彦 様
日本教育会北海道支部事務局長 蔵本 康彦 様
講演
演題 「スポーツ産業の現状と、テニスに学ぶ教育のヒント」
講師 公益社団法人日本テニス事業協会理事 スクール部会長 蒲生 清 様
札幌市でテニススクールを経営し日本テニス事業協会の理事としても尽力されている蒲生氏からは、プロスポーツや部活動のあり方、スポーツ選手のセカンドキャリア、欧米と日本での考え方の違いといった話題に具体的に触れながら、競技スポーツから生涯スポーツへの転換とスポーツ産業との関わりについて、わかりやすく興味深いお話しをいただきました。
研究発表Ⅰ(根室支部)
発表題 「職務換技能労務職員から事務長になるまで、そして事務長になってから思うこと」
発表者 北海道羅臼高等学校(現:北海道苫小牧西高等学校) 脇坂 博行
本庁講話
「高校予算グループ所管事項について」
北海道教育庁学校教育局高校教育課高校予算グループ主幹 山本 信 様
研究発表Ⅱ(釧路支部)
発表題 「学校における働き方改革『北海道アクション・プラン』(事務長版)」
発表者 北海道白糠養護学校 (現:北海道滝川高等学校) 児玉 崇志
研究発表Ⅲ(オホーツク支部)
発表題 「就学支援金って何?」にどう答えますか
発表者 北海道網走桂陽高等学校 (現:北海道旭川永嶺高等学校) 溝口 純恵
研究発表Ⅳ(十勝支部)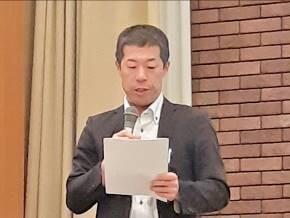
発表題 「十勝支部が考えるチーム学校への道~目指せ事務室定数プラス1.2.3!~」
発表者 北海道帯広聾学校 中村 直人
全国活動報告
全国公立学校事務長会副会長 中村 仁 様
全国公立学校事務長研究協議会の報告、全国の活動状況について報告がありました。
閉会式
閉会挨拶
北海道公立学校事務長会会長 坂井 秀昭







